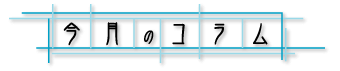
昨年十二月中旬、東京への一泊旅行から帰ってきた妻が、顔を合わせるなり土産品も手にしたままで、「すごくホッとした」と言った。日常的な旅行で、無事の帰宅から出た言葉のはずはない。「何が?」と問うと、「美しい富士山が見れて」なぜかホッとしたと言うのである。
同様の思いをした事がある。十年程前、年度末の仕事の区切りがつき、三月末にフィレンツェからアッシージ、シエナへと、何度目かのイタリア古都巡りの旅をした。伊丹空港からの帰宅途中、醒ヶ井を少し過ぎた当たりであったろうか、車窓から山桜が見えた。設計を業とする私は、帰国してもイタリア旅行の興奮が冷め切らず、日本の街並みを見ては、その都市美への不満が募るばかりであったが、山桜を見た時には何故かホッとした。
人口に膾炙したワシントンのポトマック河畔の桜を、私は未だ見たことがない。きっと「絵に描いた風景の様に美しい」に違いない。しかし、近代都市計画のデザインの美しさに感嘆こそすれ、私はその桜にホッとしたものは感じないであろう。
日本人にとって、富士山と桜は代表的な心象風景である。それゆえ、ガイドブックの表紙を飾るがごとき、名所の桜の「絵はがき」的な写真をよく目にする。しかしそれらは、均一化と平均化された消費社会の中で、象徴する対象を失った、ただ美しいだけの「富士山」「桜」と化している様な気がしてならない。
先生の写真は、私にホッとするものを与えてくれた。
見る人も なき山ざとの さくら花 ほかのちりなむ のちぞさかまし
時々、講演の依頼が入る。引き受けておきながら、自分の能力の程が分かっており、聴衆の少なさへの不安と見栄とから、友人・知人に「サクラ」を頼むことが多い。
この「サクラ」は、元は芝居の"ただ見客"のことで、パッと派手な声を掛けてパッと消えるのを、「桜」に例えたものである。転じて、大道商人言葉で、パッと集まり客を装って呷り、パッと散る人を指す。フーテンの寅さんはまさにその大道商人で、そして妹の名前に「さくら」と名付けたことを、実に気が利いていると永六輔が指摘していた。
"花はさかりに、月はくまなきのみを見るものかは。雨に対ひて月を恋ひ、たれこめて春の行方知らぬも、なほあわれに情探し。咲きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見どころ多けれ"
と、吉田兼好は厭味にもなりかねない調子で、日本人の「わび・さび」の心情を徒然草の中で書いている。万葉集や古今和歌集で詠まれた耽美な桜の姿はそこにはない。しかしながら、テーマパークなど無い昔は、花の盛りの花見こそ、庶民のディズニーランドであったにちがいない。ただ「花の本にはねぢより立ちより、あからめもせずまもりて、酒のみ連歌して、はては、大きなる枝、心なく折り取りぬ」様は、今の時代にも通用する行儀の悪さではある。
満開の「桜」の木の下で、花見客を相手に土地の友を「サクラ」にして、寅さんが商売をしている。そこへ、妹の「さくら」が尋ねてくる。さすがに山田洋二監督もそんなシーンをかき脚本はしないだろうが、パッと恋をしてパッと去ってゆくフーテンの寅さんには、やはり桜が似合うと思う。
生まれ故郷に、疾うに取り壊されてなくなってしまったが、掛川座という映画館があった。畳の座席と舞台があったから、元は劇場に違いない。その掛川座の息子と中学校で同じ組になり、裏口からそっと入って無料で映画を見たものである。
その頃、「南の島に雪が降る」という映画があった。主演は森繁久彌だったように記憶しているが定かではない。第二次大戦下、南方に兵士として送られた劇団員の物語である。戦火のおだやかな日に、慰安の為に望郷の寸劇が演じられ、紙吹雪で雪を降らす場面があり、幼心に確かに雪が降っていると感心した。
雪見障子越しに、降り積もる雪を見ながらの雪見酒から、満開の桜の下での花見酒を想い、花の色と散る様から「春にくい込んできた雪」と書いていたのは、赤瀬川原平である。
花吹雪とはよく名付けたものである。また実に美しい日本語でもある。
私は冠雪した伊吹山を背景に桜を眺めたことがまだない。やはり不可能なのであろうか。伊那谷の春は遅い。駒ケ岳をバックに光前寺のしだれ桜を見に行ってみよう。
冬などは、大垣別院前の並木が桜並木であったことなど忘れ去っている。その枯れた梢に固い花芽をつけ出してもなお気付かず、突然開花した様を見て「あっ」と思うが、楽しむ間もなく葉桜となり、枯れ梢となった頃には、また私の記憶から消えている。
久世光彦が友人の死に接し、「死んだヤツには敵わない」という一文を雑誌に寄せていた。その中で、人は死んではじめてその人の生き抜いた座標軸が決まると書いていた。確かに人の生き方の正しい評価は、未来という時間の中でしか定まるまい。ただ、五十齢を過ぎると、時の流れの無常さと、まちがいなくおとずれる死が実感でき、やり直しのきかない己の人生が突然解りだす。青春時代に、盛りの命を断つことを、桜に託して語った詩や小説を読んでは、己の「いくじなさ」に苛まれた日々の思い出とともに。
私の草花の印象は、芽がふき葉が繁り花が咲き、花はしおれて実を落とし、やがて葉も枯れ姿を消し、そして新しい芽がふく、というものである。ところが、桜は枯れ梢から葉も出さずに花を咲かせ、しおれることなく散る。突然に咲き、かつ散る潔さは、確かに桜だけのものであろう。
大垣藩の戸田家と赤穂藩の浅野家との縁の深さは、この地の人はよく知った事柄である。「花は桜木 人は武士」は、歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」で使われている台詞であり、庭の桜が散る中で、浅野匠守が切腹する場面をドラマなどでよく見かける。この台詞が「花は桜が第一で、武士は四民の第一であることを称えたまでで、桜が武士と同じではない」と論じられていることは承知しているが、花の盛りに散る潔さに生のあり様を重ね合わせるのは私だけではなかろう。
ただ、その精神史が大戦時の風潮の中で、散り際の潔さを詠った「同期の桜」へと受け継がれていったことには複雑な思いがある。己の力ではどうすることもできない時代の運命(さだめ)の中で、命を散らした若者達を思うと、「いくじなし」にはこの歌を人前で歌うことは決してできはしない。
桜花 時は過ぎねど 見る人の 恋の盛りと 今し散るらむ
梶井基次郎は、『檸檬』の中の『桜の木の下にて』で、「桜の木の下には屍体が埋まっている」と書き出している。桜の花が見事に咲くことが信じられず、埋り腐爛した屍体が流す水晶のような液体を、桜の根が吸っているからにちがいないと言った。彼の作風が「頽廃を描いて清澄,衰退を描いて健康,焦燥を描いて自若」であることの欠けらも解らぬが、この書き出しは印象強く残っている。
松岡先生に、琵琶湖北岸の桜の撮影旅行に誘われた時、「先生、桜の木の下には屍体が埋まっているんですって」と梶井基次郎のあれこれを話しながら、所用での不参加を詫びた。
それから二ヶ月も過ぎた頃であったろうか、この特集号の企画がまとまり、拙文を載せる役目をいただき、写真を受け取りながら打合せを兼ねた会食の場を持った。
先生は席に着くなり、「君に梶井基次郎を教えてもらっていて助かった。実は昨日、彼の義妹さんと話をしたんだ」とおっしゃった。基次郎には兄と二人の弟がおり、その末弟の奥さんに違いなく、先生が運営する上石津町のケアハウスに入所しているとのことであった。
「桜」がとりもった不思議な縁を感じた。
四年程前、恵那市の中山道広重美術館を設計することになり、五月の連休を使って、信州へ美術館巡りの旅に出た。
八ヶ岳を越える麦草峠に差し掛かった時、急に暗く重い雲が垂れこめ出し、季節はずれの小雪が舞いだした。信州の山並みを望める余裕もなくし、小諸への峠越えを急いだ。峠を越え少し下ると、急に目の前の視界が開けた。佐久の盆地と千曲川そしてどっしりと構えた浅間山だけが、切れた雲の合間から差し込んだ五月の明るい陽の中にあった。
“小諸なる 古城のほとり 雲白く…”と、リズミカルで美しい文語調の藤村詩集の一節が、ふいに口をついて出た。青春の過ぎ去った日々の思い出をかみしめながら小諸を目指した。
ある雑誌に、「桜の詞華集」の鼎談が載っていた。現代詩で桜を詠ったものが少ないこと、そして現代詩人の中で文語調をきちんと使える最後の人が三好達治であることを、大岡信が語り、「甃のうへ」を推していた。
「甃のうへ」
あはれ花びらながれ をみなごに花びらながれ をみなごしめやかに語らひあゆみ うららかの跫音にながれ をりふしに瞳をあげて 翳りなきみ寺の春をすぎゆくなり み寺の甍みどりにうるほひ 廂々に 風鐸のすがたしづかなれば ひとりなる わが身影をあゆまする甃のうへ
声を出して詠みたい詩である。
桜は確かに文語体が似合う。
名古屋のテレビ塔の下であったと思うが、「蕉風発祥の地」の碑がある。
芭蕉は鳴海の下里家との縁が深く、芭蕉の作風は下里家など、尾張の豪商のパトロネージによって確立されたといわれている。鳴海(熱田)と桑名は船で結ばれた旧東海道で、桑名には本家筋の下里家があり、大垣の桑名屋の下里家も全て姻戚関係にあたる
“ 命二つの中に生きたる桜かな(甲子吟行) ”
芭蕉は、郷里の伊賀上野で会えなかった門人服部土芳と、二十年ぶりに滋賀県の水口で会い、その時の歓びを「二人の命の映発と感じ、その命を分担するかのように桜が輝いている(中西進)」と詠った。
奥の細道紀行で、敦賀から近江の国へ入った芭蕉は、近江八幡から桜を詠んだ水口、そして伊賀上野へと帰るのが近道のはずである。不破の関を越えてまで、大垣へ遠廻りをしたのは、大垣の門人谷木因・如行との約束を果たすためばかりでなく、大垣の下里家、桑名の下里家への挨拶廻りがあったのであろう。そして大垣では句を詠むのも忘れる程に、大そうなもてなしを受けたに違いない。
“ 蛤の ふたみにわかれ ゆく秋ぞ ”
この句は水門川から揖斐川を下り、北陸で体調を崩して先に帰郷した曽良を訪ねた長島で詠んだ気がしてならない。大垣で「蛤」は想像しづらい。
しかしながら、門人や下里家など大垣の人々への感謝の気持ちから、つまり「心の結びの地」大垣にこの句を捧げたような気がする。
ところで、不破の関、大垣、養老、伊賀上野、吉野といえば壬申の乱の時代からある古の道で、熊野古道へと続く。また吉野には西行庵がある。
“ ねがはくは 花のもとにて 春死なむ そのきさらぎの 望月の頃 ”
辻邦生の「西行花伝」を読み返してみよう。
満開の桜の様子をみごとに詠った詞や語った文章に出会うと、建物という現示的な表現行為である設計士の私は、言葉の世界の表現者の能力にいつも驚かされる。
渡辺淳一は、「春陽の下、満開に咲き誇っている桜を見ていると、なぜともなく、『たががはずれる』という言葉を思い出す。」と書き、渡辺淳一など評価しそうもない作家が、近年まれにみる表現であると誉めていた。
確かに「けたはずれの美しさ」では、普通より抜きんでていることを強調しているに過ぎないが、桜の咲き誇る様は抜きんでているというより、どこか異常で壊れている、といった感じがあり「箍の外れた美しさ」という表現がみごとにあてはまる。これを超える表現は、当分の間出会わないような気がする。